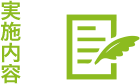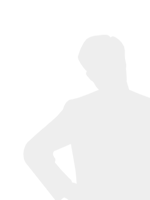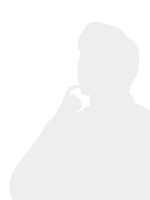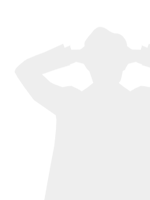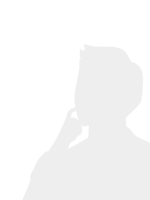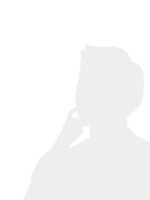高齢相続人の相続分譲渡契約の無効を主張し、自宅の取得を実現した事例

事案概要
-
依頼者
- 90代・男性(被相続人の配偶者)
-
被相続人
- 依頼者の妻
-
相手方
- 依頼者の長女
-
遺産
- 預金、投資信託、居宅不動産
-
争点
- 依頼者の相続分(50%)を長女に全部無償譲渡する契約の有効性。
相談に至った経緯
依頼者は90代の高齢男性であり、亡くなった妻(被相続人)の相続において、預金、投資信託、そして居住している自宅不動産について、本来50%の相続分を有しているはずであった。しかし、ある時、自身の相続分の全てを長女に譲渡するという契約書に署名・押印していることが判明した。
依頼者自身は、そのような相続分無償譲渡契約を行ったという認識がほとんどなく、長女が「お父さんの財産を管理してあげる」「お父さんのために預かる」と申し出たため、その言葉を信用して署名・押印してしまったようである。
その後、長女は依頼者に対し、居宅を売却するため自宅から出て施設に入居するよう告げたため、依頼者は大変困惑した。この事態を知った依頼者の弟が、依頼者と共に当事務所に相談に訪れた。
弁護士の対応
-
相続分譲渡契約の無効主張の検討と準備
- 依頼者から詳細な状況を聴き取り、90代という高齢であること、契約時の認識の有無、長女との関係性などを踏まえ、当該相続分譲渡契約の有効性を厳しく検討した。
- 長女の言動から、依頼者が契約内容を正確に理解していなかった可能性、または長女による不当な働きかけがあった可能性を指摘し、「本相続分譲渡契約は、依頼者が合理的に判断することが難しい心理状態であったことを利用して、一方的に大きな不利益を与えるもので、その失う資産の高額性、残された財産の少なさ、長女の要求内容の理不尽さ、特に相続財産の家から出て施設に入れなどは、依頼者に対する虐待に等しい結果を生じさせるなど、依頼者を精神的に追い込み、今後の生活に与える甚大な被害の発生懸念を総合考慮すると、依頼者の受ける損害はあまりに大きく、現在も不安な精神的に追い込まれ喫緊の被害が生じており、公序良俗に反しており無効であると主張した。
-
遺産分割調停の申立て
- 長女を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てた。調停において、弁護士は依頼者の代理人として、当該相続分譲渡契約は無効であると強く主張し、改めて法定相続分に基づく遺産分割を求めた。
-
調停による交渉と自宅の確保
- 長女は当初、契約の有効性を主張して反論したが、調停委員を交えた2回の調停での話し合いを通じて、弁護士は依頼者の状況と契約の不当性を粘り強く説明した。
- 依頼者自身の「自宅に住み続けたい」という強い希望を最大限に尊重し、その実現に向けて交渉を進めた。
-
調停の成立
- その結果、最終的に、相手方代理人も、早期解決を希望し、裁判になれば、相続分譲渡の有効性の決着がつくまで、遺産分割の協議も進まなくなる恐れがあり、依頼者の希望通り自宅を依頼者が取得する内容で遺産分割の調停が成立した。これにより、依頼者は自宅から退去することなく、慣れ親しんだ住まいで安心して生活を続けることが可能となった。
事件のポイント
-
高齢者の財産管理における問題の顕在化
本件は、高齢者が自身の財産に関する契約の認識が曖昧なまま署名・押印してしまい、後にそれが自身の不利益となる形で利用されそうになった典型的な事例である。高齢者の財産管理には特に慎重な配慮が必要であることを示している。
-
相続分全部無償譲渡契約の有効性の争点:
相続分譲渡契約は、相続人間の合意によって成立するが、本件のように契約当事者の判断能力や意思能力に疑義があり、内容が譲渡した側の生存権をおびやかすような場合、その有効性が争点となる。弁護士が法的な観点から契約の無効を主張したことが、解決への大きな鍵となったのである。
-
遺産分割調停による自宅確保の成功
調停は、裁判所を介した話し合いの場であり、当事者間の合意形成を促す手続きである。本件では、調停を有効に活用し、依頼者の切実な希望であった「自宅での生活継続」という目標を達成することができた。これは、法的手段を通じて生活の安定を図れた好事例である。
-
早期相談の重要性
長女による自宅売却の動きが具体化する前に弟が気づき、弁護士に早期に相談したことで、依頼者が自宅を失うという最悪の事態を回避できた。高齢者の財産問題においては、異変に気づいた家族や周囲が速やかに専門家に相談することの重要性を示唆する事例である。

■ 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
■ 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
■ 昭和50年 株式会社判例時報社入社
■ 昭和53年 司法試験合格
■ 昭和54年 株式会社判例時報社退職
■ 昭和54年 司法研修所入所
■ 昭和56年 司法研修所卒業
■ 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
■ 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
■ 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
■ 平成17年 山口県弁護士会会長
■ 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員