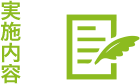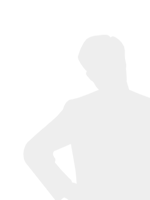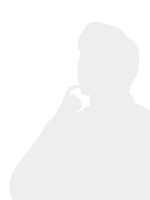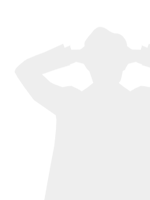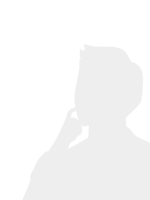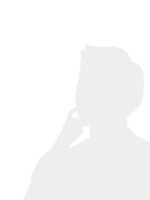遺産分割交渉における弁護士費用の負担調整により、依頼者の負担を軽減した事例

事案概要
-
依頼者
- 男性
-
被相続人
- 配偶者
-
相続人
- 依頼者を含め、配偶者の兄弟姉妹が6人
-
遺産
- 1200万円と不動産
相談に至った経緯
依頼者は、遺産分割協議を進める中で、自身の弁護士費用を全て自己負担することに不公平感を感じていた。遺産分割は相続人全員に関わる問題であり、弁護士に依頼することで全体の解決が促進されるにもかかわらず、特定の相続人のみが費用を負担するのは納得がいかないという状況であった。依頼者は、自身の負担を少しでも軽減したいと考え、弁護士費用を、まず遺産の中から差し引き、残りの遺産を分割するように協議してもらえないかということで、当事務所に相談した。
弁護士の対応
弁護士費用の負担に関する法的・実務的検討
- 遺産分割協議において、弁護士費用を遺産の中から当然に支出することは、原則として認められないことを依頼者に説明した。
- しかし、交渉の段階であれば、他の相続人全員の同意があれば、それは可能であることを説明した。
- また、依頼者の弁護士費用分ほど、遺産分割の取得分を増額内容の分割案を提案することで、実質的に弁護士費用を遺産から賄う形に調整する余地があることを提案した。
交渉段階での弁護士費用考慮の提案
- 相手方相続人に対し、遺産分割協議の円滑な進行と早期解決に、依頼者が努力しているので、依頼者の負担する遺産調査、相続人確定の調査費用、実費、弁護士費用の一部を、依頼者の取得分を増額する形で調整することを提案した。
- 具体的には、依頼者が取得する遺産分割額を、通常の法定相続分より遺産調査、相続人確定調査費用、戸籍などの入手費用、遺産分割の弁護士費用相当分ほど多めに設定した遺産分割案で合意するよう交渉した。
交渉による合意形成
- 弁護士が交渉を重ね、相手方相続人の理解と同意を得ることに成功した。
- これにより、依頼者は遺産分割において、自身の弁護士費用を実質的に賄えるだけの多めの遺産を取得することができ、経済的負担が大幅に軽減された。
ポイント
交渉段階での柔軟な対応の可能性
遺産分割調停や審判といった裁判手続きでは、弁護士費用を遺産から支払うことや、相手方に負担させることは原則として認められない。しかし、交渉段階であれば、当事者間の合意によって、遺産分割の取得分を調整することで、実質的に弁護士費用を考慮した解決を図ることが可能である。
依頼者の経済的負担の軽減
弁護士費用は決して安価ではないため、その負担が依頼者にとって大きな懸念となる場合がある。本件では、弁護士が遺産分割の調整役として、早期で円満に進行できるので、相手方たちも事務的な負担が軽減できることを喜び、分割協議もまとまり易く、その結果、依頼者の経済的負担を軽減し、安心して弁護士に依頼できる環境を提供できた。
弁護士の交渉力の重要性
このような弁護士費用の負担調整は、相手方相続人の理解と協力が不可欠である。弁護士が、交渉を通じて相手方にメリット(相手方は、遺産分割協議書の取りまとめもせず、株式や預金の解約手続という大変な事務手続きもしないまま、代理人から入金を待つだけという恩恵を受けること)を提示したり、公平性を訴えたりすることで、合意形成へと導く交渉力が重要となる。

■ 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
■ 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
■ 昭和50年 株式会社判例時報社入社
■ 昭和53年 司法試験合格
■ 昭和54年 株式会社判例時報社退職
■ 昭和54年 司法研修所入所
■ 昭和56年 司法研修所卒業
■ 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
■ 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
■ 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
■ 平成17年 山口県弁護士会会長
■ 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員