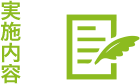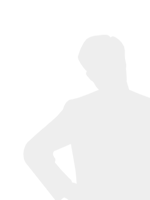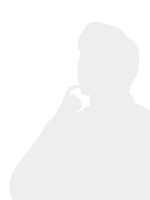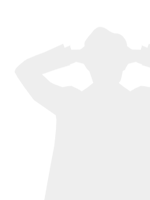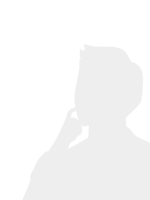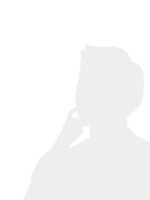特別縁故者の申立てにより、被相続人への貢献が認められ財産分与を実現した事例
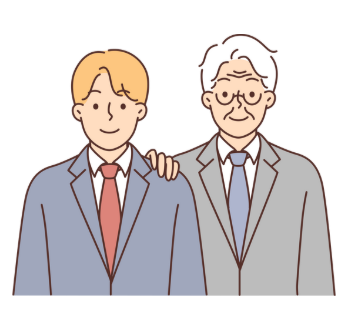
事案概要
-
依頼者
70代・男性である(被相続人の従兄弟であり友人)。 -
被相続人
- 依頼者の従兄弟で、友人
-
相手方
- 財産分与請求は、相続財産清算人。祭祀承継者指定の調停は、被相続人の姉。
-
遺産総額
-
2,000万円である。
-
争点
- 特別縁故者としての財産分与請求、および祭祀承継者の指定。
-
相談に至った経緯
依頼者は、亡くなった従兄弟(被相続人)が精神疾患で入院中に、頻繁に面会に訪れて、同伴で外出することに協力もして、精神的な支えになっていた。また、生前には「被相続人の先祖のお墓の管理や墓仕舞い」も頼まれていた。更に、被相続人の自宅の片付けも献身的に行っていた。
また、被相続人の精神疾患の症状が進行した際には、依頼者が後見開始の申立ての手続きをサポートし、最終的には弁護士が後見人に選任された。その際にも、依頼者は、被相続人が入院していた精神科の医師にも状況を説明し、後見開始の申立に必要な情報提供を行った。被相続人の死後、依頼者はお墓の管理や墓仕舞いをするため、自身が被相続人の祭祀承継者となることを希望し、あわせて生前の貢献を理由に財産分与の申立てを希望し、当事務所に相談した。
弁護士の対応
-
祭祀承継者選任申立てと財産分与請求の準備
被相続人の相続人である弟がいたが、借金の可能性があると判断したため相続放棄手続きをした。そこで、弁護士が依頼者を祭祀承継者とする申立書を家庭裁判所に提出した。
-
特別縁故者としての貢献の立証
- 依頼者による被相続人への長年の入院先への見舞いによる精神的な支え、生前の約束(お墓の管理と墓仕舞い)、自宅の片付け、被相続人の葬儀の手配をする等、被相続人の生前及び死後にわたって一貫して精神的・物質的支援を継続してきたことの具体的な貢献事実を詳細に立証するための証拠収集と書面作成を行った。
また、被相続人が閉鎖病棟にて生活をしており、自宅に戻れる希望もなかったので、依頼者の面会を喜び、それ自体治療的効果があったこと、被相続人は、依頼者の面会の機会に依頼者と一緒に外出できることも生きる上で心の支えになり、依頼者の面会訪問をとても喜んでいた事実を病院での医師から説明を受けて、丁寧にまとめ、依頼者の貢献度合いを明確に示した。
-
調停・審判を通じた交渉と解決
- 裁判所での調停で依頼者が祭祀承継者として適格であることを主張し、相手方と協議のもと祭祀承継者になった。また審判手続きにおいて、依頼者の特別な貢献と祭祀承継者としての立場から被相続人の先祖の墓の管理や墓仕舞いの費用も相当かかることを指摘し、遺産から十分な財産分与の必要性を訴えた。
-
解決の実現
- その結果、裁判所の判断により、遺産2,000万円のうち、1,000万円が依頼者に分与されるという画期的な結果を得た。
事件のポイント
-
特別縁故者への高額な財産分与が認められた稀なケース
通常、被相続人への長年の世話があったとしても、遺産のうちごく一部(例えば10年間お世話をしても、1,000万円の遺産に対して100万円程度)しか財産分与が認められないケースが多い中で、本件では遺産の約50%に相当する1,000万円が依頼者に分与されたことは特筆すべき点である。これは、依頼者の被相続人に対する精神的な支え、具体的な身の回りの世話、自宅の整理、後見申立ての協力、そして生前のお墓の管理や今後の墓仕舞いの約束といった多岐にわたる献身的な貢献が、裁判所によって高く評価された結果である。
-
祭祀承継者の地位が財産分与に影響を与えた点
依頼者が祭祀承継者となり、お墓の建立費用や毎年の維持費用を負担する義務が生じる点も、今回の財産分与額の決定において重要な考慮事項とされた。祭祀承継者としての負担を考慮し、それを補填する形で財産分与が認められた点も、本件の大きなポイントである。
-
弁護士の専門性と交渉力が貢献
特別縁故者の財産分与という、なかなか多くを認められない問題に、弁護士が間に入り、依頼者の貢献を法的に整理し、裁判所や他の相続人に対して明確に主張できたことが、この成功的な解決に繋がったのである。
-

■ 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
■ 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
■ 昭和50年 株式会社判例時報社入社
■ 昭和53年 司法試験合格
■ 昭和54年 株式会社判例時報社退職
■ 昭和54年 司法研修所入所
■ 昭和56年 司法研修所卒業
■ 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
■ 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
■ 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
■ 平成17年 山口県弁護士会会長
■ 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員