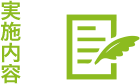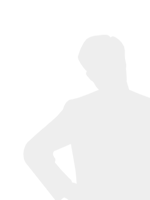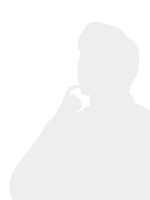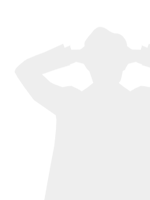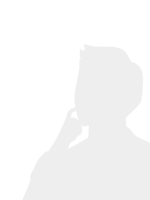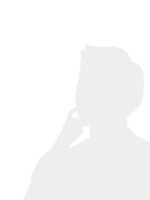介護貢献を理由とした相続分減額交渉により、遺産分割を円満に解決した事例

事案概要
-
依頼者
- 70代・女性
-
被相続人
- 依頼者の夫
-
相手方
- 被相続人の前妻の子
-
遺産総額
- 預貯金2,000万円
-
争点
- 依頼者の介護貢献を理由とした、相手方の相続分減額交渉
相談に至った経緯
依頼者は70代の女性であり、夫が遺言書を作成することなく亡くなった。夫には前妻との間に子がおり、その子(相手方)は法定相続人である。依頼者と前妻の子は、夫の生前からほとんど接点がなく、疎遠な関係であったため、夫が亡くなった際も、前妻の子が存在することを依頼者が失念していたほどである。
夫の相続分は、依頼者が2分の1、前妻の子が2分の1となるはずであった。しかし、依頼者は夫の晩年、献身的に介護を行ってきた。この介護の貢献を考慮すれば、前妻の子が法定相続分どおりの遺産を取得することは不公平であると感じていた。そこで、依頼者は、自身の介護貢献分を主張し、前妻の子の相続分を可能な限り減額したいと考え、当事務所に相談した。
弁護士の対応
介護貢献の事実と遺留分減額の法的根拠の整理
- 依頼者から夫の介護に関する詳細な状況を聴き取り、介護期間、内容、依頼者の負担度合いなどを具体的に整理した。
- 介護貢献が相続分減額の交渉材料となる法的根拠(寄与分など)を検討し、依頼者の主張はもっともと考えた。ただ、裁判所が認める厳密な寄与分の要件は満たしていなかったが、交渉では十分に説得力があると考えられた。
相手方との交渉開始と遺留分減額の提案
- 相手方である前妻の子に対し、依頼者の代理人として接触し、夫の介護における依頼者の多大な貢献を説明した。
- その上で、依頼者の介護貢献を考慮し、前妻の子の法定相続分を50%減額する具体的な提案を行った。
粘り強い交渉と合意の形成
- 当初、相手方は遺留分の減額に難色を示したが、弁護士は依頼者の状況と介護貢献の事実を粘り強く説明し、公平な解決の必要性を訴えた。
- 依頼者の年齢や今後の生活状況も考慮に入れ、相手方にも理解を求める交渉を続けた結果、最終的に相手方は相続分を50%減額することに同意した。
遺産分割協議の成立と手続き
- 合意内容に基づき、遺産分割協議書を作成し、預貯金2,000万円の分割手続きを滞りなく完了させた。
事件のポイント
介護貢献による相続分減額交渉の成功
介護は、相続において寄与分として評価される可能性があり、相続分減額の交渉材料となり得る。本件では、依頼者の献身的な介護貢献を具体的に主張し、相手方の理解を得ることで、相続分を減額するという依頼者の希望を実現できた。
交渉による円満解決の実現
遺言書がない状況で、疎遠な関係の相続人との間で遺産分割トラブルが生じたが、弁護士が間に入り、感情的な対立を避けつつ、交渉によって双方にとって納得のいく解決を図ることができた。
高齢依頼者の負担軽減
70代の依頼者が直接、疎遠な相手方と交渉する精神的負担を避けることができた。弁護士が代理人として交渉を全て担うことで、依頼者は安心して手続きを進めることができたのである。

■ 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
■ 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
■ 昭和50年 株式会社判例時報社入社
■ 昭和53年 司法試験合格
■ 昭和54年 株式会社判例時報社退職
■ 昭和54年 司法研修所入所
■ 昭和56年 司法研修所卒業
■ 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
■ 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
■ 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
■ 平成17年 山口県弁護士会会長
■ 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員